東急歌舞伎町タワーの館内には、いたるところに歌舞伎町や新宿の歴史や多様性を表現するモチーフがちりばめられている。JAM17 DINING&BARも、そのひとつ。ダイニングへ続く壁一面にはアナログレコードがディスプレイされているが、これらをセレクトしたのは、新宿に所縁のある5人のアーティスト。
彼らは新宿にどんな想いを抱き、レコードを選んだのか。そして彼らが新宿に感じる“GROOVE”とは? 第4回となる今回は、MONDOさんにお話を聞いた。
[連載:『あなたが思う“GROOVE”』‐6組のアーティストたちが選盤したレコードを紹介]

新宿・歌舞伎町に2023年5月に誕生したHOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel。お客さまの滞在が、各エンターテインメント施設や新宿のまちと呼応した“高揚感”に包まれるよう魅力ある音楽を意味する“GROOVE”がホテル名の由来。開業にあたり、新宿や歌舞伎町にゆかりのある6組のアーティストを選者に招き、「JAM17 DINING & BAR」にてレコードを展示。選者それぞれにとっての『あなたが思う“GROOVE”』を探っていく。
MONDO
自分自身を探求する中で生まれた “ヒゲ女装”というスタイルで、アーティストのLiveツアーやMVに出演するドラァグクイーン。
DJとしてクラブや各種のレセプションパーティーに出演するほか、ボディワーカーとして音楽を使ったワークショップを開催。
「心を開いて音楽によりそった時、僕たちは自由な音になれる。音になった僕たちは自分を信頼し、自分を許し、自分に感謝することができる。」
自由に踊ることの喜びをシェアしている。
音にまつわる記憶が織りなす「新宿のサウンドトラック」。
MONDOさんが選んだ5枚のレコード

─ MONDOさんが選んだ5枚のレコードについて聞いていきたいと思います。どんな基準や方向性でセレクトしましたか?
ひと言で言うと「サウンドトラック」。そして「音にまつわる記憶」がテーマになっています。音楽って、いつの時代・どこで誰と聴いたとかが、すごく記憶に残るものだと思うんですよね。ごく個人的な、過去の自分にとってのサウンドトラックでもあり、この新宿・歌舞伎町という街のサウンドトラックにもなるように選びました。
さらに、このタワーのホテルに泊まる方たちが聴く音楽として──彼らの人生のワンシーンを彩るサウンドトラックになるように、そんな思いも込めています。
<MONDOさんがセレクトした5枚がこちら>
セレクトした5枚のレコードは、3つのカテゴリに分けられるのだそう。それぞれ、詳しくお話してもらった。
──自身の記憶につながる音
1.Lenny kravitz/Mama Said(1991)

2.Lauryn Hill/The Miseducation(1998)

この2枚はまさに、僕自身の記憶・記録と結びついている“サウンドトラック”です。
レニー・クラヴィッツの2nd『ママ・セッド』。リリース当時は高校生でしたが、いまだにこのアルバムはよく聴きますね。旅先で聴く機会の多い作品でもあって。どこにいても、自分の居心地のいい場所に戻ってこられるような……落ち着く音楽なんです。すごく好きな1枚で、名盤だと思っています。
ローリン・ヒルのソロアルバム『ミスエデュケーション』は僕が上京して、ちょうどこの新宿界隈でDJをやっていたころに発売された作品です。こちらもどこで誰と聴いたとか、僕自身の記憶がすごく詰まっている作品。
このころ僕は初めての同棲を経験したのですが、恋人がかけてくれるローリン・ヒルで目覚めた朝が何度もあって。その人の顔、一緒に暮らした部屋だったり、そのときの気持ちだったり……すごく思い出させてくれる音楽です。
その人は今では特別な友達ですが、当時はすごく辛い別れ方をしてしまいました。でも、その苦さを含めて自分にとっては宝物のような記憶なんだと思います。いい思い出だけじゃなくて、辛かったり悲しかったりした経験こそ、今の自分をサポートしてくれる気がする。そんな感覚をくれる1枚ですね。
──眠らない街を見下ろしながら
3.Keith Jarrett/The Köln Concert(1975)

ジャズピアニスト、キース・ジャレットのライブアルバムで、名盤といわれる1枚。こちらも僕が旅先でよく聴く音楽です。歌舞伎町を訪れた人が、街の景色を眺めながら聴くBGMになればいいなと思って選びました。
20代半ばのころ、原宿でギャルソンのバイトをしていたのですが、その店内で流れていたのがこの作品との出会い。そこで過ごす人の邪魔をしない、でも不意に感覚をひらいて耳に音楽が飛び込んできたとき、すごく心地いい音色で……。すべて即興演奏で構成されていて、キースの“在り方”というのかな。その存在感が、音に現れている感じがします。
ですが、のちにキースは体を壊してピアノを弾けなくなってしまって。片手でしか演奏できず、両手演奏のピアノ曲を聴けば非常にもどかしく感じ、シューベルトや何かソフトな演奏を聴いたりするだけでもうんざりして「自分はそこまで回復する見込みもない。」と悔しさと苦しみを露わにしたそうなんです。その話を知った同時期に、上皇后の美智子様もピアノが弾けなくなったというエピソードを目にしたのですが、美智子様はというと「今までできていたことは、『授かっていた』もの。それができなくなったことは『お返ししたもの』」とおっしゃっていたんですね。
音楽を通して、まったく違うおふたりの生き様をひしひしと感じた出来事です。もちろんどちらがいい、という話では全然ないのですが、僕にとってはキースの「悔しい」という気持ちがとてもリアルで、生々しくて。すごく人間らしいエネルギーを感じて、好きなんですよね。
その人間らしさを、この歌舞伎町という街に投げ込んでみたい気持ちもありました。
──境界を超える“GROOVE”
4.芸能山城組/AKIRA オリジナル・サウンド・トラック(1988)

5.Steve Winwood/Steve Winwood(1977)
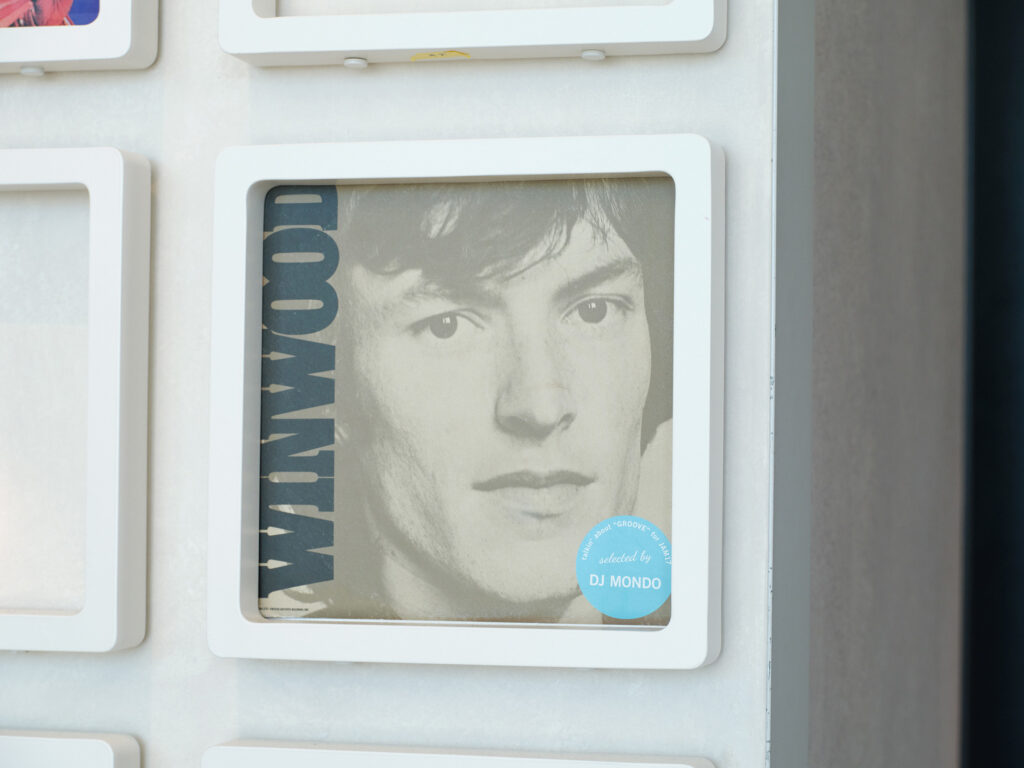
先にご紹介した3枚は、「俯瞰で街を眺めるサウンドトラック」というイメージ。新宿での体験を回想しながら、ホッとした瞬間に流れるような。旅人がホテルで窓の下に歌舞伎町の喧騒を見下ろしながら、スターバックスの窓際でシネシティ広場の人の往来を眺めながら……そんなふうにひとりで自分自身にもどる時間のための音楽です。
対してこちらの2枚は、まさしく新宿を歩いている最中にガンガン流れてほしい音楽ですね(笑)。
この2作品に、僕は2つの共通点を感じています。1つ目はそれこそ(当連載のテーマにもなっている)“GROOVE”です。『AKIRA』は中学1年、スティーブ・ウィンウッドは高校1年のときに出会いましたが、音が高まり、回転するイメージ……周囲を巻き込んで徐々に高揚していくグルーヴ感。それをはっきりと体感した作品でした。
そして2つ目の共通点は、「文化を超越している」こと。
芸能山城組は日本のパフォーマンスコミュニティですが、バリ島の「ジェゴグ」の要素を取り入れている。スティーブ・ウィンウッドは白人だけれど、黒人音楽の影響を大きく受けていて、R&Bやソウルの要素で音楽を作っています。
そこにはもちろんリスペクトがあり、憧れや愛があって。僕がやっている「性別を超越してみる」という遊びにも、通じるものを感じるんです。こんなふうに何かを超越したり、ミックスしていく文化って、すごく歌舞伎町らしいんじゃないかな。






